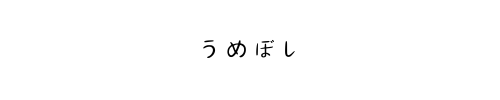税務調査が終了すると、その結果に基づき、必要に応じて、課税庁による更正処分や決定処分などの第2次税額確定権限が発動されます。
この課税庁による更正処分や決定処分ができる期間は定められており、その期間のことを「除斥期間」といいます。今回はこの「除斥期間」について解説します。
また、課税庁は課税処分を行うとき、課税処分を行うための情報を集めるために事前に税務調査を行います。しかし、納税者が税務調査を拒んだり、調査しても帳簿書類がなかったり、帳簿書類が信用できるものではないような場合、帳簿の金額(実額)に基づいて課税処分を行うことが不可能となります。このような場合に他の資料を入手して納税者の所得額を推計して課税処分をするということが行われます。これを「推計課税」と言います。つまり、「推計課税」は課税処分の一形態ということです。
この「推計課税」についても解説します。
課税処分の除斥期間
✔除斥期間の概要
税務調査が終了すると、その結果に基づき、必要に応じて、課税庁による更正処分や決定処分などの第2次税額確定権限が発動されます。
この課税庁による課税処分(更正処分や決定処分など)ができる期間は定められており、その期間のことを「除斥期間」といいます。
この「除斥期間」は原則として「法定申告期限から5年」となります(国税通則法70条)。
この「除斥期間」の間であるなら、課税庁は何度でも課税処分を行うことができます。
また所得税㉟「申告納税方式の趣旨、期限、期間など」でも述べたように、この「除斥期間」は時効ではありません。したがって、完成猶予(期間の進行が一時的にストップすること)や更新(期間の進行がリセットされてゼロに戻ること)の制度はありません。
✔例外的な除斥期間
上で述べたとおり、除斥期間は原則として「法定申告期限から5年」ですが、除斥期間の例外規定が設けられており、以下の場合は「法定申告期限から5年」の除斥期間が延長されます。
除斥期間が延長される例外規定
① 偽りその他不正行為により免れた国税に関する課税処分(更正処分、決定処分)の除斥期間
② ある年分の所得税に関する課税処分が判決などにより変更された場合の除斥期間
③ 所得税額の計算の基礎となる事実が無効であることに基因して税額が変更された場合の除斥期間
④ 通常の除斥期間満了直前の6か月以内に更正の請求がされた場合の除斥期間
① 偽りその他不正行為により免れた国税に関する課税処分(更正処分、決定処分)の除斥期間
偽りその他不正行為により免れた国税に関する課税処分(更正処分、決定処分)は法定申告期限から7年間(国税通則法70条4項)行うことができます。
また、判例によると、課税処分にかかる税額の一部が「偽りその他不正の行為により免れた」ものであれば、それ以外の部分についても全て除斥期間は7年になるとされています。
そして、国税について「偽りその他不正の行為」を行った者が、納税者本人ではなく、納税者の秘書や納税者の顧問税理士などであったとしても、除斥期間は7年間となります。
さらに「偽りその他不正の行為」により確定申告を行うことにより免れた国税があったが、後日、自ら修正申告を行って免れた国税を納税したとしても、当該国税の除斥期間は7年となります。つまり、その修正申告に誤りがあれば、その除斥期間の7年以内であれば、当該修正申告につき更正処分を行うことができます。
② ある年分の所得税に関する課税処分が判決などにより変更された場合の除斥期間
たとえば、ある年にある事業者が事業用建物につき修繕を行い、その支出を必要経費として計上し、確定申告をしました。しかし、課税庁から当該支出は建物(資産)として計上し、減価償却を行うべきとして課税処分を受けました(つまり、修繕に係る支出を必要経費ではなく、資産として計上すると所得税額も変わる)。
その課税処分につき、当該納税者は納得がいかないので、不服申立を行い、その結果、当該支出は必要経費であるという判決が下りました。そうすると、課税庁が行った課税処分による所得税額には誤りがあったことになるため、これを修正する必要があります。
しかし、課税処分の除斥期間は、国税の法定申告期限から5年間であるため、この期間を経過してしまっていたら、課税処分ができないことになります。そこで、判決の日が除斥期間を経過していても課税処分ができるように、その判決などの日から6か月間は課税処分を行うことができることとしています(国税通則法71条1項1号)。
③ 所得税額の計算の基礎となる事実が無効であることに基因して税額が変更された場合の除斥期間
たとえば、ある年にある事業者が1000万円の売上を計上し、その年の確定申告を行いました。しかし後に、その1000万円の売上に係る取引が無効になりました。そうすると、1000万円の売上を前提に行われた確定申告は結果的に間違っていたことになるので、これを修正する必要があります。
しかし、課税処分の除斥期間は、国税の法定納期限から5年間であるため、これを経過してしまっていたら、課税処分による修正ができないことになります。そこで、その無効となった日から3年間は課税処分を行うことができるとしています(国税通則法71条1項2号)。
④ 通常の除斥期間満了直前の6か月以内に更正の請求がされた場合の除斥期間
通常の除斥期間(法定申告期限から5年間)満了直前の6か月以内に納税者から更正の請求が行われた場合、これに対する課税庁の課税処分は、その更正の請求があった日から6か月間行うことができます(国税通則法70条3項)。これは、更正の請求ができる期間を実質的に確保するための規定と考えられます。
推計課税
✔推計課税とは
税務調査を行っても、課税庁が課税処分を行うのに必要十分な情報が得られないことがあります。
税務調査は任意調査であり強制力がないため、たとえば、納税者Aが調査を拒否すれば、Aから課税処分を行うための情報を入手することが不可能です。
このような場合に、調査を拒否したAに対して適切に課税しなければ、真面目に申告したり調査に協力している納税者との間で課税の不公平が生じます。
そこで、Aに適正に課税するため、課税庁はAから情報を得られない場合、他の資料をもとにAの所得額を推計しAに課税処分を行います。これを「推計課税」と言います(所得税法156条、法人税法131条)。
✔推計課税のやり方
それでは、推計課税は具体的にどのように行うのでしょうか。
基本的には「反面調査+同業者比率」により推計課税を行います。
具体例を2つあげて説明します。
具体例1 スーパーマーケットA店の広告やチラシを印刷している印刷所を経営するBさんの所得額の推計
BさんはA店の広告やチラシを印刷して、それをA店に売却して対価を受けているので、A店を反面調査すれば、Bさんの売上を把握することができます。
そして、Bさんの同業他社を複数選び、収入に対して必要経費が何%かかっているのか(経費率)を調べてその平均を出します(この平均を「同業者比率」といいます)。
そして、反面調査で把握したBさんの売上に、この同業者比率を適用することで、Bさんの所得額を計算し、これに課税します。
具体例2 広く一般人を顧客としているクリーニング店を営むCさんの所得額の推計
Cさんは広く一般客を顧客としているため、反面調査でCさんの収入金額を把握するのは困難です。
一方、クリーニング店は電力やガスなどのエネルギーを使って業務を行っているため、これらの消費額と収入金額には、ある程度比例関係があると想定されます。
そこで、Cさんのエネルギー消費額を反面調査によって把握します。他方、Cさんの同業他社を複数選び、エネルギーの消費額に対して収入額や所得額はどれ位の割合なのかを調査して、その平均(同業者比率)を求めます。そして、Cさんの消費額にこの同業者比率を適用することにより、Cさんの所得額を推計し、これに課税します。
✔推計課税の適用要件
実額主義
推計課税を定めた規定には一切現れませんが、課税庁が行う課税処分は「実額を用いて行う課税処分が原則で、推計課税で行う課税処分は例外」であるというルールが妥当していると考えられます。
このように、課税処分を「実額を原則、推計を例外」とする考え方を、ここでは「実額主義」と呼ぶことにします。
推計課税の要件
課税処分は「原則、実額を用いて課税を行い、例外的に推計課税を行う」ことになります。つまり、実額を用いて課税処分できないとき、推計課税を行うということです。
では、どういった場合に実額を用いて課税処分ができないのか、すなわち推計課税が必要となるのか。以下のいずれかの要件を満たした場合「実額を用いて課税処分できず、推計課税が必要」となります。
推計課税の要件
以下のいずれかの要件を満たす場合、推計課税を行うことが必要となる
① 実額で所得を計算できる帳簿書類がないこと
② 存在する帳簿書類が不正確で信頼できないこと
③ 納税者の非協力により税務調査ができないこと
上記の①~③の場合は、実額を用いて課税処分ができないため、推計課税が必要になります。
適切な推計課税を行うための要件
「推計課税の要件」の①~③のいずれかの要件を満たせば実額を用いた課税処分ができないので、推計課税が必要になります。
しかし推計課税を行う必要が生じた場合に、その推計課税がいい加減なものであっては適切な課税処分は実現しません。
そこで、推計課税が適切に行われることを担保するために、推計課税を行うにあたっては以下の要件をすべて満たす必要があります。
適切な推計課税を行うための要件
推計課税を行うときは、以下の要件をすべて満たさなければならない
① 適切な資料を用いていること
② 適切(合理的)な計数を用いていること
③ 個別性を適切に考慮していること
①と②は相対的な性格が強いと言えます。
たとえば、先ほど見た印刷所を営むBさんと、クリーニング店を営むCさんに用いるべき①適切な資料や②適切な計数(同業者比率)は、それぞれで異なっており、これらは絶対的なものではありません。
③は、たとえば同業者比率を求める場合、同業者を幅広く調査すると、その中には対象となる納税者とかけ離れた人も対象としてしまうというデメリットがあります。他方、その対象となる納税者と酷使している同業者だけをピックアップし、同業者比率を求めようとすると、そのサンプル数が少なくなってしまうというデメリットがあります。
つまり、推計課税を行うにあたって、サンプル数を多くすると、対象となる納税者とかけ離れた人も対象となってしまうし、反対に対象となる納税者と酷使している同業者だけをピックアップするとサンプル数が減少してしまうという、トレードオフの関係にあるのです。
③はつまり、サンプル数を増やすだけでなく、質も考慮して下さいということを言っているのです。
✔実額反証
たとえば、課税庁はDさんの事業所得について、推計課税を行いました。課税庁は反面調査によってDさんの収入金額は1000万円であると明らかにし、これに同業者の調査から得られた同業者比率を適用して、必要経費が600万円、所得が400万円と推計しました。
Dさんは、この推計課税による課税処分を不服として、不服申立を行いました。内容は「課税庁が主張する売上1000万円は認めます。でも必要経費は帳簿書類等によって700万円であることが分かったので、経費を700万円所得額300万円として所得税を計算しなおして下さい」という申立です。
つまり、課税処分は実額で行うのが原則であり、推計課税は実額で行うことができない場合に限って行われるべきであり、Dさんの事例の場合、売上1000万円は実額、必要経費700万円も実額であるから、この両方の実額でもって所得額を計算することが理にかなった所得税の計算方法ということになります。
このようなDさんの主張を「実額反証」と言います。
これに対して裁判所は「Dさんが真実の所得額が推計の結果を下回ると主張するためには、経費についての実額の主張・立証のみでは足りず、売上金額もその全てを実額でもって主張・立証する必要がある」と判決しました。
つまり、課税庁が反面調査によりDさんの収入金額を把握するのには限界があり、しかし、その限界の中で課税庁はDさんの所得額を推計課税している、すなわち課税庁はやれることはやった上で課税処分を行っているため、課税庁による推計課税は尊重されるべきだという判決であるように思われます。
最後に
今回は、課税処分の除斥期間と推計課税を解説しました。
国税は、除斥期間だけでなく、国税の徴収権の消滅時効も絡むので、所得税㉟「申告納税方式の趣旨、期限、期間など」と合わせて復習すると、この辺の理解が進むと思います。
また、推計課税はそれ自体が課税処分であり、本来は課税処分を受けるような状態にしないことが重要です。やむを得ず課税処分を受ける場合でも、推計課税ではなく実体課税を受けるようにすべきと考えます。そのためにも日頃から帳簿を正しくつけておくべきです。
なお、青色申告者は青色申告の承認を取り消されない限り、推計課税の対象にはなりません。